 このシリーズでは、今まではどちらかと言うと応募者側の視点で「より良い職場選び」に言及してきました。
このシリーズでは、今まではどちらかと言うと応募者側の視点で「より良い職場選び」に言及してきました。
しかし、就職活動という「戦い」に勝利するには、まず相手の戦略(職場がどんな人材を求めているか)を知る必要があります。
そこで、ここから数回にわたり、雇用者ないし現場スタッフ(選考者側)の目線で「応募者に求められるスキルとは何か」について考察していきたいと思います。
《スポンサーリンク》
1.PTに求められる適性要件とは?
まず一般論として、理学療法士(PT)に求められる適性要件ってどんなもの? ということに関しては、過去記事でも私なりに考察していますが…
要約すると、以下のようになります。
◆地道に努力する粘り強さ
◆人間に対する興味・関心
◆接遇・コミュニケーション能力
◆観察力・気配り能力
◆協調性・リーダーシップ
◆事務処理能力
◆幅広い分野の知識・経験(ジェネラリスト)
これらはPTにだけ特別に求められる要件というよりは、人に直接かかわることの多い職種にはほぼ共通の必要条件と言えるのかもしれません。
あくまでも「理想像」として、ではありますが…。
私は過去10年程、部署長として、療法士やリハビリ助手の採用担当者をつとめてきました。
あえて「新卒PT」に求められる第一要件を上記の中から抽出するとしたら、やはり協調性(同職種・他職種間を問わず)ではないかと考えます。
2.知識・技術は「及第点」で良い
どうして、新卒PTに求められる第一要件が「協調性」だと言えるのでしょうか。
PTとしての知識や技術は、それほど重視されないのでしょうか?
もちろん専門職としての知識・技術は、優れていればそれに越したことはありません。
ですから、選考過程で「成績証明書」は必ず提出して頂きます。
養成校や実習先でどのような事を学んできたのか、履歴書に記載していればその内容にもしっかり目を通します。面接でも、それは必ず確認します。

しかし私としては、知識・技術は「及第点」であればよいと思います。
「及第」とは、臨床実習をクリアしたPTの学生として、平均的なレベルに達していればよいという意味です。
そもそも現在のPT養成校のカリキュラムでは、
卒業時点で、「独立して理学療法が行える」という状態を目標とはしていない
のが現状です。
「上位者(上司・先輩)の指導・監督の下、理学療法が実施できる」というのが、卒業(就職)時点での現実的な到達目標とされています(決してそれが良いこととは思いませんが…)。
入職した次の日から「即戦力」を期待された20年前の私の時代とは、隔世の感がありますね…。
だから、というわけでもないのですが、知識・技術は採用者側にとって選考の第一要件ということにはなりません。
それはなぜでしょうか?
3.なぜ「協調性」が一番大切?
もとより、新卒者には「臨床経験」がほとんどありません。
誤解を恐れずに言ってしまえば…
専門職としての知識・技術は、ある程度の経験を積み重ねることによって初めて実用的に活用できる。
患者さんの最前線に立つ臨床のPTとは、そういうものです。

なので、知識・技術の優劣は、入職の時点ではそれほど問題ではありません。
地道に努力する人・自発的に学ぶ心のある人は、最初はダメでも、3~5年も経てば「努力を怠る成績優秀者」を追い越してしまいます。
PTの知識・技術だけでは、多くの患者さん(とくに高齢者など)にとっての最大のニーズである「住み慣れた地域で、安全かつ安心して、自分らしく生活していける」という望みには応えられません。

徒手的リラクゼーション・ストレッチ・モビライゼーションなど、PTが有する技術は患者さんの身体の痛みや機能障害を改善させることを目的としています。
けれども、筋力の向上や動作能力の改善などもそうですが、実施した次の日にすぐ結果が出るということはほとんどありません。
理学療法とは、それほど万能ではないのです。
むしろ、高齢者・進行性疾患の方など、リハビリを行ったからといって必ず改善するとは限らない対象者と向き合う場面の方が多いです。
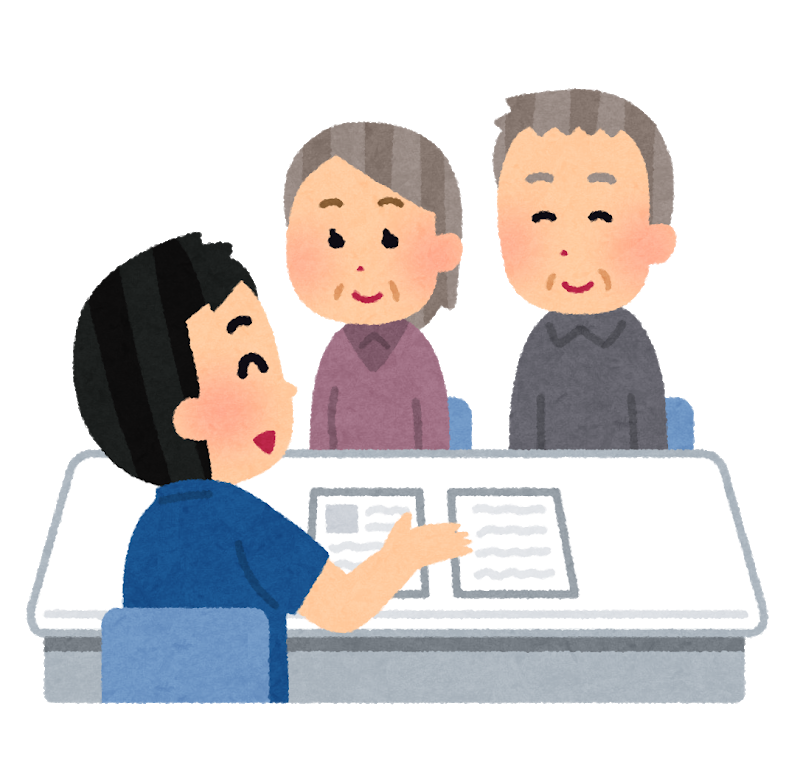
そういった方々には、在宅医療(かかりつけ医受診・訪問看護 etc)、その他介護保険サービス(福祉用具・訪問介護 etc)、ご家族や地域住民の支援など、あらゆる社会資源を活用し、チームでアプローチしていくことが必要になります。
それゆえに…
◆応募者側は、人間関係の良い職場を求める。
それと同様に、
◆雇用者側・現場スタッフ側は、コミュニケーション能力が高く、同職種・他職種と良好な協調関係が築ける人を求める。

これもまた当然のことと言えるでしょう。
ちなみに、えらそうな事をここで書いている私もPTという職業を選んでさんざん苦労したのですが、それは「コミュニケーションによる協調」という面で大きくつまずいたからです…(泣)。
4.スタンドプレーヤーはいらない
前述のように、多くの専門職や支援者がチームとして機能することで、包括的なリハビリテーションの提供が可能になるわけです。
◆患者目線:患者さんへのチームアプローチを可能にする。
◆職員目線:無用な人間関係のトラブルを防ぐ(職場の秩序を乱さない)。
この2つの意味で、協調性はたいへん重要なものです。

繰り返し申し上げますが、PTその他の医療従事者は、純然たる「職人」ではありません。
治療技術さえ優れていれば無愛想で礼儀知らずでも良いということは、あり得ないのです。
周りと協調できない「スタンドプレーヤー」は、医療・介護の現場には不要というのが現実です。
《スポンサーリンク》
5.履歴書・面接における自己PR

履歴書に記載する内容や、面接試験の場においても、前記のことを念頭に自己PRをするのが望ましいでしょう。
例えば…
◆学内での成果
⇒グループワークで難しい課題に取り組み、チーム一丸となって一定の結果を出した。
◆実習時の成果
⇒現場の医療専門職の方々が多職種で協同・連携しているのを見て、大いに触発された。
⇒担当医師・病棟看護師・医療ソーシャルワーカー・ケアマネージャーなど、他職種の情報を積極的に聞き取り収集することで、担当患者さんのアセスメントに活かすことができた。
こういうことがアピールできれば良いのではないでしょうか。

また、面接で「将来どんなPTになりたいか?」とか「この職場でどのように働きたいか?」といった質問をされることもあるでしょう。
そういう時、自分なりの考えをしっかり持って即答できるなら、どんな答えでもそう問題はないかと思います。
ただ、私の個人的な考えではありますが…
「患者さんのそばに寄り添いたい」
とか、
「患者さんやご家族の方から感謝されるようなPTになりたい」
というような、抽象的で漠然とした…悪く言えば「自分目線」「自己満足」のような将来像は、あまり好印象ではありません。
医療従事者は、病気や怪我で苦しむ人がいるから成り立つ職業です。
いわば、「他人の不幸を飯のタネにしている」わけですから、
①あくまでも患者さんの幸福追求が第一。
②そのために、PTとして必要なスキルを向上させたい。
③この職場でそれを実現させられるよう、積極的に学んでいきたい。
④具体的には、◯◯といった知識や経験をまず習得していきたい。
このような順序で、具体性を伴った将来像を語ることができればベターでしょうね。
「学ぶ」ということに関しては、職員教育が充実していることが職場を選択する上で大切であることを前回の記事で述べました。
しかし、
「患者さんにいろいろ学ばせて頂きたい」
「職場のなかで教えてもらいたい」
こういう受け身的な言い方もあまり好ましくはありません(もちろん、診療場面のなかで患者さんから教えられることは多いのですが…)。

たとえ新人であっても「国家資格者」であり、それで収入を得るわけです。
学生の頃と違い、自分が学ぶために周囲がお膳立てしてくれるのが当然ではありません。
自発的に学ぶ姿勢を前面に出していく人の方が、採用する側にとって頼もしく感じるのは言うまでもないでしょう。
こうあるべき! というような理想論を振りかざし過ぎたかもしれませんね…申し訳ございません(汗)。

最初の職場へのエントリーに際して、選考者側により良い印象を与えるとともに、就職にあたっての心構えも持っておいて頂けたらと思い、駄文を書き連ねてみました。
次回は、一定の経験を有するPTの転職について、同じく「選考者側の視点」から考察してみたいと思います。
最後までご覧下さいましてありがとうございました m(*- -*)m
《スポンサーリンク》