 介護老人保健施設では、おもに入所・通所・訪問のリハビリを提供しています。
介護老人保健施設では、おもに入所・通所・訪問のリハビリを提供しています。
今回は、入所の利用者さんに対してリハビリを行なう際に、必ず確認する3項目についてのお話しです。
チェックというほど大袈裟なものではありませんが、私が日々の業務で大切にしている内容なので、少しお付き合い頂けると幸いです。
※リハビリ開始時のチェックポイントとしては、まず利用者さんの体調などが挙げられますが、これは医療・介護従事者として当然の話なので割愛します。
《スポンサーリンク》
1.3つのチェックポイント
入所リハビリは、居室内などの生活空間で行なわれることもありますが、どちらかと言うと専用のリハビリ室で実施する場合が多いです。
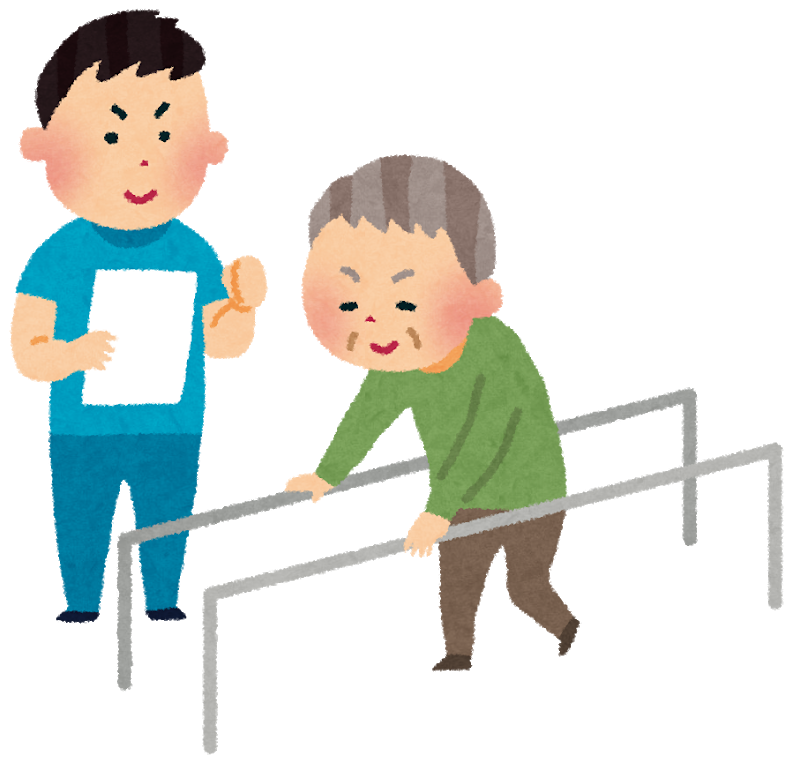 私は非常勤のPTとして週3回勤務していますが、職場から求められる業務は「とにかく利用者さんのリハビリを数多くこなすこと」です。
私は非常勤のPTとして週3回勤務していますが、職場から求められる業務は「とにかく利用者さんのリハビリを数多くこなすこと」です。
※物を扱うように「こなす」という表現をしてしまい、利用者さんやご家族の方々には申し訳ない気持ちですが、ここではあえて使わせて頂きます。
実際、1名の利用者さんに対して費やすことのできる時間は、居室~リハビリ室の送迎も含めて概ね20分です。

リハビリに対し消極的ないし拒否的な利用者さんであれば、「その気にさせる」ための導入的コミュニケーションにもかなりの時間を要します。
どうにかエレベーターに乗り、リハビリ室までご案内したら、必ず確認するのが以下の3項目です。
①車いすの汚れ
私は勤務の関係上、入所の方々には昼食以降に介入します。

昼食後や15時のおやつ後に介入すると、利用者さんの車いすや衣服には多くの食べこぼしが付着しています。
食事動作の自立度や認知症の程度などにもよりますが、時には座面クッションの下が味噌汁でベチャベチャに濡れていたことも…。
その状態で、何時間も放置されている場合もあります。
そういった利用者さんの車いすをよく見ると、下図の赤い部分に、長期間にわたって降り積もった食べカスがこびりついていたりします。

◆シート(座面)の隅
◆シートパイプ(座面を支えるサイド部分)
◆フレーム下部
◆フットサポート(足を置く台)
治療用ベッドへ移乗して頂いた後、私は時間の許す限り、これらの汚れを拭き取ります。
クッションの洗濯・乾燥など、その場で手に負えない場合は入所スタッフに申し送るようにします。
②タイヤの空気圧
 車いすのチェック項目はさまざまです。
車いすのチェック項目はさまざまです。
ブレーキの効き具合や各部のネジの緩みなどは、リハビリ室までの道中やベッドへの移乗時にクイックチェックします。
中でも放置されがちな不具合が、空気圧の低下です。

入所定員は100名なので、私1人で毎週全ての利用者さんのリハビリを行なうわけではなく、担当者も固定ではありません。
そのため、一部の方々には1ヶ月ぶりに介入するという場合もあるのですが…恐らくかなりの長期間、タイヤがベコベコに凹んだ状態で使われていたのだろうな、と思われるケースに当たります。
リハビリ室で空気を補充したら、最後にブレーキ操作を利用者さんにも試して頂きます。
何故なら、空気圧が増すことで、高齢者の腕力ではブレーキが掛けにくくなることもあるからです。
これは安全上、チェックすべき必須ポイントです。

空気注入バルブの「虫ゴム」が劣化している場合は、補充してもすぐに空気が抜けてしまいます。これも要チェックです。
注入バルブの根元にある六角ナットもきちんと締めておかなければ、タイヤチューブの根元がヒビ割れる原因となります。
③メガネの汚れ
利用者さんは無意識に顔やメガネを触るため、レンズがベトベトに汚れていることがほとんどです。
そのまま掛けていると、さらに視力が悪化しそうです。 リハビリ室では必ずメガネを外して頂き、洗浄します。
リハビリ室では必ずメガネを外して頂き、洗浄します。
もちろん専用の洗浄液などありませんから、水と中性洗剤で汚れを流し、布で軽く拭き取ります。
いきなり澄んだ世界に戻った利用者さんは、たいていニッコリ笑って喜んで下さいます(^_^)
<その他>

上記①・②は車いすの利用者さんに関してですが、歩行補助具を使用されている場合はもちろんチェック対象となります。
歩行器であれば、同じくネジの緩みやブレーキの効き具合・注油状況など。
杖であれば、支柱の凹み・曲がり・グリップの割れ・先ゴムなどの確認です。
2.なぜ見過ごされてしまうのか?
これらの管理不十分については、私が勤めた数カ所の介護施設にほぼ共通のような気がします。

理由として考えられるのは、
◆人手不足
◆管理責任者が実質的に不在
◆決まり事(ルーティンワーク)になっていない
◆社会的責任・人としての愛情が足りない
といったところでしょうか…。
車いすの清掃などは、利用者さんがベッドや普通のいすで休んでいる時を狙って行なわなくてはなりません。
時間帯や曜日を決めて当番制で行なうなどのルーティン化が必要なのでしょうが、人手不足の中で過酷な労働を強いられている介護職の方々にとっては、なかなか難しいことです。

空気圧などのメンテナンスに関しては、「車いす安全整備士」という認定資格を有する事務職員が時々点検してくれている、と入職時に聞いたことがあります。
が、その職員も他に複数の業務を兼任しており、定期的に全ての車いすを点検・整備しているわけではないようです。
明確な故障・破損でない限り、実質的にはほとんど対応できていないように思われます。
利用者さんの所有物については、衣類や義歯などは施設である程度管理がなされています。
 けれども、それ以外の持ち物については見過ごされている場合が多いようです。
けれども、それ以外の持ち物については見過ごされている場合が多いようです。
というより、保守責任の範疇を越えているからでしょうか…。
メガネの洗浄などは、その代表と言えます。
また、車いすも歩行器も、利用者さんの個人所有物と施設の備品が混在しており、メンテナンスに関する責任の所在を不明確にしている要因なのかも知れません。
全ての事象の背景には、人手不足による多忙という現実があるのでしょう。
 私自身、利用者さん1名当たり20分というリハビリ介入時間の中で、これら3項目への対応を完璧に行なうのは難しいです。
私自身、利用者さん1名当たり20分というリハビリ介入時間の中で、これら3項目への対応を完璧に行なうのは難しいです。
前述のように私には「数をこなすこと」が求められているため、清掃などに時間を掛け過ぎるわけにはいきません。
事実、20分以上掛かってしまうことも多いため、カルテ記載の時間を短縮するなどして帳尻をあわせ、何とか所定の人数をクリアしているのが実状です。

職場のリハビリスタッフは概ね良心的な方々なので、私がメガネを洗浄しているのを見て眉をひそめる…というようなことはありませんが、かと言って「すなおさん、良いことをしているなぁ…」とも思われていないフシがあります。
ひょっとすると、「それ、療法士がやることじゃないよ」と冷ややかに見ている人もいるのでしょうか…。
しかし、「療法士でなければ誰がやるの?」となると、う~ん…と唸るしかありません。
《スポンサーリンク》
3.「人手不足」で済ませてはいけない
私も非常勤職員なりに色々と感じるところはありますが、職場への提案の仕方には充分な配慮が必要だと考えています。
実行するとなると、結果として常勤の介護スタッフの業務負担を増やすことにもなりますから…。
ただ、車いすの清掃やメンテナンスは衛生・感染管理および安全面からも重要ですので、何でもかんでも人手不足のせいにするのではなく、必要なことはしっかり決め、約束事に従って業務を遂行すべきでしょう。
まさか、「どうせすぐに汚れるのだから」と放置しているのではないでしょうね…そう願います。

個々の医療・介護従事者として、気づいた時にその都度対応する責任感。
そして利用者さんの立場や心情に配慮する「人間としての優しさ」が、最も基本的であり大切な要素ではないかと思う今日この頃です。
最後までご覧下さいましてありがとうございました m(_ _)m
《スポンサーリンク》