 昨今、がんなどの命に関わる病気について、治療の開始が遅れたことにより寿命を縮めてしまう…という例がよく取り沙汰されています。
昨今、がんなどの命に関わる病気について、治療の開始が遅れたことにより寿命を縮めてしまう…という例がよく取り沙汰されています。
患者さん側にも「健康に対する意識づけが不十分」だったケースも時にはあるかもしれません。
しかしその一方、医療従事者側にも「問診・視診・触診」といった古典的ではあるものの非常に重要な診察法をおろそかにし、「検査偏重主義」に陥っている面もまた大きいのではないでしょうか。
そこで今回は、患者さん・医療者双方にとって望ましい問診のあり方について考察してみたいと思います。
《スポンサーリンク》
1.『問診』は重要な診察法

まずは、「問診とは何か」を改めて整理しておきましょう。
『医師などの医療従事者が、患者さんに対して直接、現在の自覚症状や今までの生活歴(職歴・家族の病歴等)、および既往歴などを聴取する診察法』
おおよそ上記のように定義されます。
本当の「名医」と呼ばれる医師は、診断において「問診8割・身体的所見1割・各種検査1割」と言われるほど、問診を重視しているようです。
私はPTですが、患者さんから直接得られる情報の中でも、やはり問診は重要項目と位置づけ、相当な時間を割いています。
また私自身、治療を受ける側の体験を通して「患者さんの訴えに耳を傾けることの大切さ」を痛感したものです。
2.問診における「5W1H」
「5W1H<表1>」は、医療従事者にとって問診項目を明確にするためのツールとして用いられますが、患者さんにとっても、自身の身体症状を整理し医療者側へ伝える上で役立つことと思います。

ここでは、よくある「腰痛」の症状を例として話を進めていきますが、どのような疾患でも基本は同じです。
皆さまが病院を受診し、問診を受ける際の参考になれば幸いです。
①Who(だれが?)
これは「自分自身」であることがほとんどでしょう。
ただ、親や子どもの受診に付き添う際や、家族の病歴を話す場面などでは思わぬ誤解を生むこともあるので、主語を明確にしておきましょう。
②What(何が?)

おもな症状が何であるかを言葉で表わします。
腰痛に関して言えば、単純に「腰が痛い」だけでなく、しびれ・皮膚感覚の鈍さとか、患部の熱っぽさなどを伴う場合もあります。
これらは全て、腰痛の原因疾患や病状・病期(急性期~慢性期)を予測する上で重要となります。
③Where(どこが?)
もっとも多いと言われる「非特異的腰痛(原因疾患が不明確で、不良姿勢や無理な動作・精神的ストレスなどが背景要因とされる)」では、腰周囲や臀部の痛みに留まる場合も多いです。

その一方、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、腰から足の方へ向かっている神経が圧迫を受けるような疾患であれば、その神経が支配している部位(第4~5腰椎から出ている神経なら、ふくらはぎの外側など)に痛みや感覚のマヒが起こることもあります。
そういうわけで、症状が出現している場所の特定は診断上、必要不可欠です。
腰から遠く離れた部位の症状であっても、関連性がある場合も考えられますので遠慮せず伝えるようにしましょう。
④When(いつ?)

<いつ頃から?>
3日前から突然生じた激しい症状、ということであれば、急性期であり早急な医学的対応が必要になることもあります。
1ヶ月前から断続的に起こっていて症状に著明な変化がみられない場合であれば、慢性期に差しかかっているとも考えられます。
医療従事者側に説明する際は、「2~3日(1~2ヶ月)ぐらい前からかなぁ…」といった曖昧な答え方は避け、できる限り詳細に述べるようにしましょう。
<どんな時に?>
夜間じっとしていても痛みがあるならば、急性炎症が起こっている可能性があります。
長時間歩くとだんだん足の痛みが強くなる「間欠性跛行」が生じている場合、脊柱管狭窄症もしくは閉塞性動脈硬化症などが疑われます。
⑤Why(なぜ?)

専門的には「発症(受傷)機転」とも言いますが、要は「腰痛を起こしたきっかけ」です。
「早朝に重い荷物を持ち上げた瞬間、グキっと…」といったようなことですが、そこからも原因疾患や病状を予測することができます。
ここで逆説的に言えることは、「とくに腰を痛めるきっかけが見当たらず、身に覚えも無い」という場合も、事実としては大変重要なのです。理由は後述します。
⑥How(どのように?)
患者さんが感じる「主観的な痛みの種類」と言えばよいでしょうか。
「重だるい」→腰周囲の筋肉の過緊張(肩こりのようなもの)
「キリキリする・刺すような」→腰の表層よりも深い部位の問題(内臓など)
「足先まで走るような」→神経根など、末梢神経の圧迫・損傷による痛み
「ズキズキする・脈打つような」→急性炎症による痛み
一概には言えませんが、このように予測されます。
痛みはまさに「自覚症状」なので他者から客観的に捉えるのは難しいのですが、このような擬音語まじりの主観的な表現は意外に重要ですので、恥ずかしがることはありません。

実際、言葉で形容し難い腰痛の背景には、腎・尿管結石のような疾患、あるいは脊椎の感染・腫瘍といった重篤な病気が隠れていることもあります。
このような場合、前述のように「3日前に突然発症」とか「きっかけが無く、身に覚えも無い」ということもあり得ますし、注意深く問診すると「筋肉の過緊張」などとは全く違う種類の痛みであることが推察できます。
3.患者さんに求められる「問診票への詳細な記入」
いかがでしょうか。
ひとくちに「腰痛」と言っても、重大な疾患も含めた多くの可能性が想起されるというのがお分かり頂けたと思いますし、「問診の重要性」にも気づかれたことでしょう。
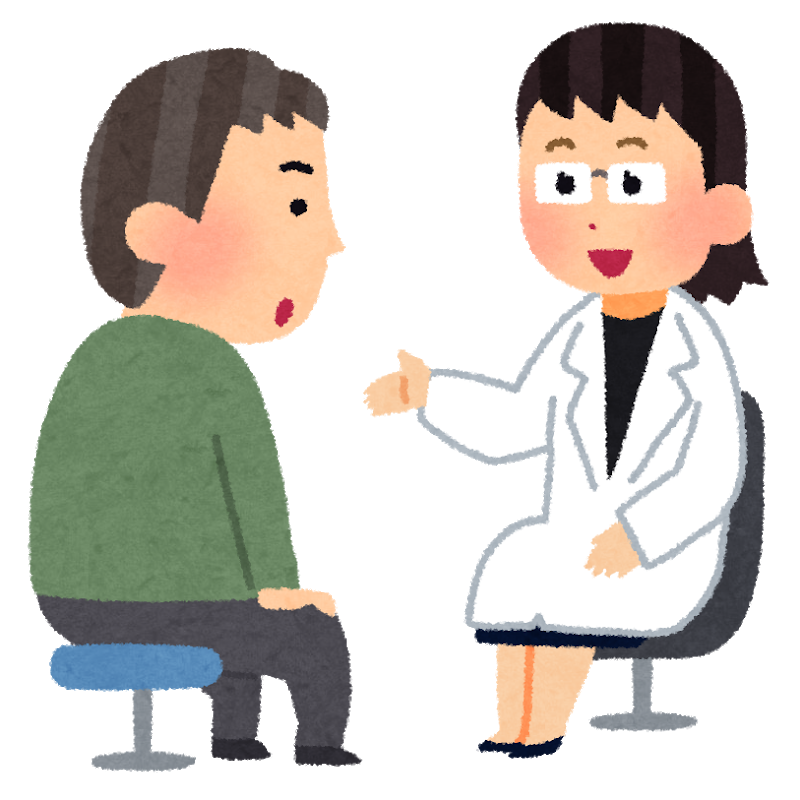
ただ単に
「腰が痛いんです…」
というよりも、
「腰の右側のあたりが、3日前からキリキリ痛むんです。夜も痛くて眠れません。とくに身に覚えは無いのですが…」
と述べたほうが、相手にうまく伝わりますよね。
ろくに患者さんの訴えに耳を傾けず、電子カルテの画面ばかり見ながら
あ~そう。3日前から腰がね…。他はとくに何もないのね?
じゃ、とりあえず湿布を1週間分出しとくから、それで様子見てね。
というような、問診をおろそかにする医師(その他医療従事者)は全く信用できないと言い切ってしまいましょう。
PTの私が言うのも何ですが…医療機関および医療従事者は全ての病気を治してくれるわけではありませんし、誤診することもあり得ます。
自分の健康を自身で守るためにも、受診にあたっては「5W1H」に沿った症状の経過・現在の状態をメモして持参するくらいの慎重さは必要ですし(さまざまな理由で不可能な方には申し訳ありませんが…)、問診を軽視するような病院(医療従事者)は選択しない方が無難です。

もちろん、ほぼ全ての病院において、待ち時間に「問診票」を記入するよう促されると思います。
問診票の書式にもよりますが、持参したメモに基づき、できるだけ詳しく記入することを推奨します。
まともな医療従事者なら、ビッシリ記入された問診票を「鬱陶しい」と感じることはなく、むしろ有り難いと思うことでしょう。
最近では、ホームページから各診療科の問診票をダウンロードできるようにしてくれている病院もあります。可能なら自宅でアウトプットし、前もって記入しておくのも良いでしょう。
私が検索した中で、比較的よくできていると思われる2病院の問診票をご紹介しておきます。
※ちなみに私は以下の病院に受診したことは1度もございませんので、医療機関としての評判などは承知しておりません。悪しからずご容赦下さい。
5W1Hのところでは述べませんでしたが、これらの問診票に共通する
◆既往歴・治療歴・手術歴
◆服薬歴・アレルギー
◆妊娠の可能性(女性の場合)
なども大切ですので、漏れなく記入しましょう。
《スポンサーリンク》
4.医療従事者に求められる「問診スキル」
ここからは、医療従事者の方々へ向けての提言になります。
5W1Hに基づく問診は、もちろん「患者さん自身が努力してまとめておくこと」というよりも、まず医療従事者が「問診スキル」として身につけておくべきことであるのは言うまでもありません。
ほとんどの患者さんはこちらの都合の良いようには話して下さいませんので、ある意味うまく誘導しながら必要な答えを引き出さなくてはなりません。
患者さんに対して「腰痛のきっかけ」を伺った際、
あぁ…とくに思い当たることは無いねぇ…。
と返答されたからといって、
あ、そうですかぁ、分かりました。じゃ、とりあえずベッドに横になって下さいね。
などと、分かりもしないのに適当に返事をして、とりあえず腰をマッサージして、ついでに腰痛体操も指導するようなPTは全く論外です。
実際そういう人もいるので、同業者として情けない限りです。
 腰痛の多くは長期間にわたる腰部への負担が蓄積して、ある時に一気に顕在化するものです。
腰痛の多くは長期間にわたる腰部への負担が蓄積して、ある時に一気に顕在化するものです。
例えば過去の職業歴やスポーツ歴は、その患者さん自身はそれが「きっかけ」とは思っていなくても、実際には現在の慢性腰痛につながっていることも大いに考えられるのです。

「自分は事務職で、重労働ではないから関係ない」と患者さんが思っていたとしても、実際は「長時間座りっぱなし」のデスクワークのほうがむしろ腰痛に悪影響を及ぼしていることも少なくありません。
なので、私はそれらの情報は問診票の記入内容にかかわらず、必ずこちらから質問し、聴取します。
職業に関してはプライバシー(機微な個人情報)という側面もあり、中には「あまり答えたくない」という人もいらっしゃるかも知れませんが、そこは
「職業や過去のスポーツ経験が、◯◯様の腰痛に影響している場合もございますので…」
と前置きしてからお尋ねすれば、ほとんど問題になることは無いでしょう。
5.さいごに…医療従事者は「熱意と共感」を!
ともかく、患者さんの訴えを尋ねる際には、愛想笑いとか無駄な相づちなどといった「小手先のコミュニケーションスキル」はあまり必要ではありません。
◆診察室(リハビリ室)に入室する際の歩行状態をよく観察する。
◆イスに座って問診を受けている時の表情や、座位姿勢を観察する。
◆訴えにじっくりと耳を傾け、必要に応じてうなずく。
◆得られた大事な情報は、その場で記録を取る。
◆うまく表現できない時は、補足・誘導するなどして必要な答えを導き出す。
このように「しっかりと観察しながら熱心に耳を傾け、導く姿勢」こそが、何よりも大切です。
その真心は必ず患者さんに伝わりますし、それで信頼を得ることができればその後の治療・リハビリも円滑に進められるのです。

患者さんの痛みや困り事に共感し、ともに向き合い治療に臨む姿勢を持つことが大切ですね。
今回の記事が、患者さん・医療従事者の双方にとって『問診』の重要性を再認識するきっかけになれば幸いです。
最後までご覧下さいましてありがとうございました m(_ _)m
《スポンサーリンク》